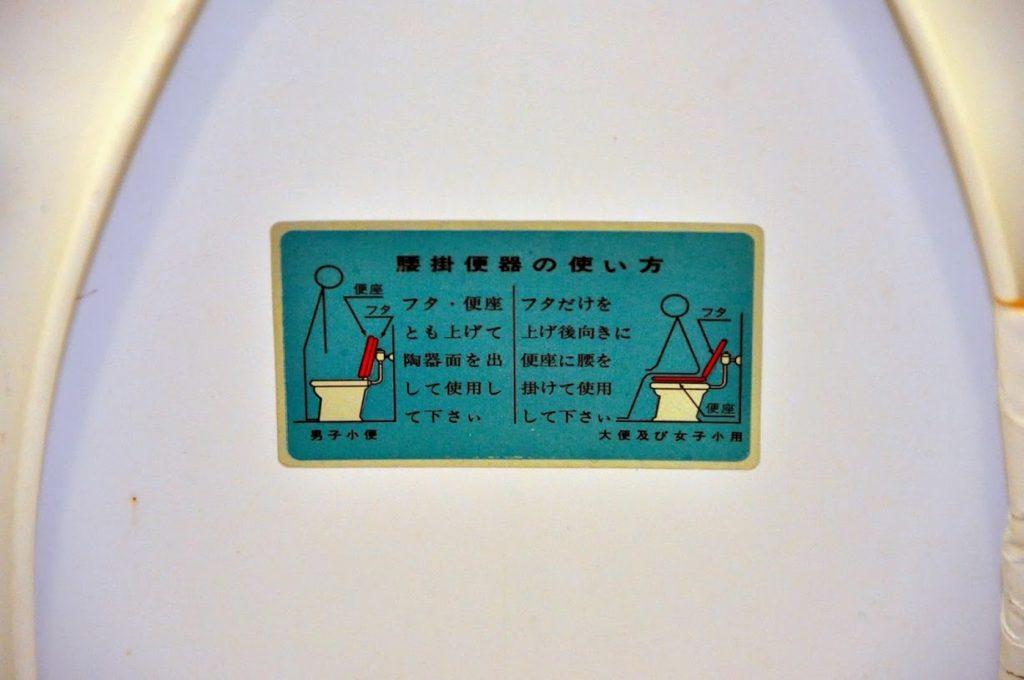今、ジビエが熱い。
各地でイノシシや鹿を加工調理して、レストランやお土産として供されるようになった。

今ではお洒落な食材として盛んに良いイメージで売り出し中だが、半世紀前の私がまだ子供の頃にも、シシ肉、シカ肉をはじめ、カエルやスズメ、ウズラ、兎肉は食べられるところはあった。

ところで普段では食べない「かわり種」食材として好きな人は好きだが、一般には目を背けられる、あるいは外国人から見ると奇異に思われるものもある。
馬肉、ナマコ、ホヤ、むつごろう等。
鮮魚の活き作りや割いて焼くウナギの蒲焼きなども、外国人から見れば、俗にゲテモノ食いと言われることもある。

鯨肉に至っては、政治問題化してしまうほど食材と文化は密接な繋がりがあり議論が絶えない。
しかし、ゲテモノという呼称は、我々が勝手にそう呼んでいるだけで、ここでは「かわり種食材」と呼ばしてもらう。

ここからは「閲覧注意」なのだが、私がこれまで食べたことのある「かわり種食材」を挙げてみると、
熊の掌、駱駝のコブ、象の鼻、ヤギの乳、ワニ、ヘビ、ダチョウ、サル、センザンコウ、アリクイ、ハクビシン、赤狗、猫、ネズミ、サソリ、アリ、ミミズク、鳩、キジ、野うさぎ、コブラ、シカ生肉などを覚えている。

そのほとんどが1980年代前半の中国広東省か雲南省である。
この頃までは、「広東では四つ脚で食べないのはイスとテーブルだけ」と豪語し、「かわり種食材」のことを「野味」と言って普通に食べていた。
広州には野味香餐庁という由緒ある料亭があり、清平路という通りの市場には、生きたアリクイやサルなどさながら動物園のようで、普通に路上で売っていた。

それが改革開放政策、アジア大会や北京オリンピックの開催、SARSの流行などで一遍に姿を消してしまった。(前述の清平路の野味市場はペットショップに様変わりして再び売っていたのを見て中国人の商魂の逞しさに驚嘆した。)

それでも今では、広州でもペットブームで野味は批判の的になっていると聞く。コロナ禍の今だから、尚更そうであるに違いない。

食は世につれ、世は食につれ。である。